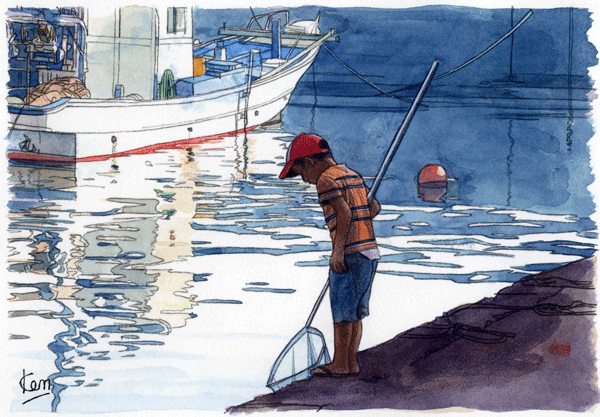| 絵は感動を表現するメディアです。
夕焼け小焼け・・・と誰もが知っている「赤とんぼ」の歌に、何故か日本の郷愁を感じていたのですが、この歌のどこに人を引きつける力があるのか疑問に思い、調べたことがありました。
そこで思わぬ発見をしました。
「赤とんぼ」は大正10年に発表されたもので、作曲は山田耕作、作詞は三木露風によってつくられました。
夕焼け小焼けの赤とんぼ おわれてみたのはいつの日か
山の畑の桑の実を 小かごに摘んだはまぼろしか
十五で姐(ねえ)やは嫁にいき お里の便りも絶えはてた
夕焼け小焼けの赤とんぼ とまっているよ竿の先
この歌詞は露風自身の幼少時代の思い出を素直に書いたものと言われています。
露風が5歳の時両親が離婚することになり、以降母親とは生き別れで祖父に養育されることになったのですが、その子守り奉公のねえやに面倒を見てもらうわけで、そのときの印象を歌詞にしたのです。
だから「おわれてみたのは」を漢字で書けば「追われてみたのは」ではなく、「負われて見たのは」であり、ねえやの背中におんぶされて肩越しに見た夕焼け ということになります。
ねえやといっても15歳で嫁に行ったのですから、当時の農家は赤貧のため口べらしもあっての子守り奉公で、しばらくして嫁いでいったわけですが、嫁入り先の農業労働力として働きづめの一生を送ったのではないでしょうか。
また、「お里の便りも絶えはてた」の意味は、お母さんは離婚し実家に出戻ったのですが、実のお母さんがわが子を不憫に思い、実家の近くの娘をねえやとして子守り奉公に出すように図ったのです。
それにより彼はねえやからお母さんの便りを聞くことが出来、母さんもねえやから息子の便りを聞くことが出来たのですが、嫁に行くことで、もうお母さんの消息も途絶えてしまったことを言っています。
私たちは「赤とんぼ」を唄うとき、そんな深い意味は汲み取ることは到底不可能ですが、なんとなく歌詞の狭間から熱き想いを感じ取ることが出来るからこそ、この歌が日本人の郷愁として残り続けてきたのではないでしょうか。
露風は作詞家となり幼少時代の鮮烈な思い出を歌詞にしたのですが、もし彼が画家になっていたら、その万感の思いを込めて絵にしたと思います。
もう会うことが出来ない母への切ない未練の心を秘めながら、真っ赤な夕焼けを背景にいる赤とんぼの絵・・・その絵を観る人はそこまでの事情はうかがい知る由もないのですが、単なる赤とんぼの絵以上のもの、その絵から離れがたい何かを感じるに違いありません。
感動を表現することは絵の命なのです。
いい絵は絵画技術やテクニックを超越して、描き手の感動や思いが、絵からにじみ出るものなのです。
子供の描いた絵に光るものがあるのは、技術レベルを超えて、子供のほとばしる感動が素直に表現されているから、うまい下手を超えて、引きつけられるのではないでしょうか。
この本では絵画技術のみならず、感動の育て方や、感動の引き出し方までも考えていこうと思っています
|